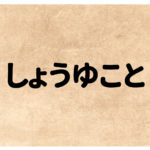目覚まし時計の音が聞こえた。
しばらく聞いていなかったこの音が、わたしに学校生活という現実に突きつけた。
そう、今日は始業式の日だ。
まだ春休みだったらいいのに、と思う気持ちは、わたしのあくびの回数に反映されているようだった。学校に着くと、下駄箱付近にクラス分けの表が貼り出されていた。
各学年ごとに人だかりができていて、それぞれグループごとに盛り上がっているようだった。人だかりをかき分けて、わざわざ自分の名前を探すのも面倒だな、と思いながらまたあくびが出た。
この時間がなければ、もうちょっとゆっくり寝られたのに。毎日時間割だ、連絡事項だ、とかいってデータ配信してるくらいなんだから、クラス分けだってデータでくれたっていいじゃないか。変なところで古臭いんだよなあ、この学校。
「遥夏、おはよう~」
「……おはよう。」
眠そうな挨拶をするわたしを見て、部長はにやけていた。
「……そんなに変な顔してた?」
「いや、相変わらず眠そうだなあと思って。」
部長は笑いながらわたしにそう言った。部長は、翠の次くらいにわたしの評論家だ。
「部長、何組だったの?」
「私はB組、遥夏も同じだよ。」
部長はそういいながら掲示板のB組のあたりを指差した。B組の紙を見ると、わたしの名前のすぐ下に「大平優子」と書いてあった。その名前を見つけた瞬間に、1年生だった時のことを思い出して、ため息が出た。
「また部長に後ろからつつかれるのか……」
「いや、寝てる遥夏が悪いから。」
露骨に落胆するわたしに、部長はまた笑いながら言ってきた。そんないつも通りの部長の姿を見て、部長が同じクラスなら一安心だ、と胸をなでおろした。
他の部活のメンバーも何人かいれば、ひとりぼっちになることはないだろう。そう思ったところでふと、なんでこんなにひとりぼっちを恐れているんだろう、と思った。
部長だって、部活のメンバーだって、友達であることには変わりはないし、誰かしら同じクラスになる確率だって高い。それなのに、どうしてこんなにも、わたしは不安だったんだろうか。
「あ~あ、これで高塚さんもいたらもっと面白かったのにな~。」
「……そっか、翠、いないんだった。」
春休みは、翠が学校にいないということを、すっかり忘れていた。部活で学校に行くことはあったけど、所属している部活が違う翠がいないのは当り前だった。お互いが暇な時は、くだらない連絡や長電話をすることもあった。ある意味身近に感じられていた翠の存在が、学校生活の中では物凄く遠く感じられた。
「そんなに落ち込まないでよ~。高塚さんの分も、私が起こしてあげるよ。」
「ええ?翠は部長と違って、起こすときペンでつつかないもん。部長はお断りだわ。」
「ちょっと、私の扱い雑。大事にしてよ。」
部長はすかさずわたしに文句を言ってきた。その様子を見て思わず笑いがこみあげてきた。笑うわたしを見て、部長もつられて笑っていた。
「おーい、全員移動しろー。遅刻扱いにするぞー。」
生活指導の先生の一声で、その場にいた生徒全員が、ゆっくり移動を始めた。
移動速度の遅さは、きっとみんなの素直に先生の声に従いたくない気だるい感情が反映されているのだろう。わたしと部長も、顔を見合わせた後、へらへらと笑いながら同じ教室へ向かって歩き出した。
高校生活最後の一年が、ついに始まった。