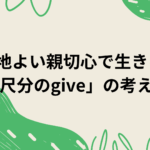どのくらい時間が経ったのか、考えるのを忘れるくらいに翠と話を続けていた。話す頻度が減っても、顔が見えていなくても、ずっと話をできるのは、翠しかいないんじゃないだろうか。お互いくだらない話で笑い合ったあと、翠が唐突に話を変えた。
「そういえば、遥夏ちゃん、手紙書いてくれた?」
「あ~……手紙……」
「絶対書いてないでしょ。返事待ってるのに。」
翠に不意を突かれて、わたしはたどたどしい返事しかできなかった。翠のむくれた顔が、頭に浮かんできた。ちらりと、机の上の日記帳を見た。日記帳の下に、そっと忍ばせたままだ。2か月くらい、そのままにしている気がする。
「よく覚えてるね、結構前じゃん。」
「覚えてるよ。遥夏ちゃんに、ちゃんとしたお手紙書いたの初めてだし。返事待ってるのに。」
もう、という翠の声が聞こえてきた。なんだか申し訳なくなって、背中が丸くなっていく。
「じゃあ、今月中に書くよ。……多分」
「多分って。約束してよ。絶対書いてね」
「ええ、良いじゃん別に。電話してるし、メッセ送ったりしてるじゃん。」
「遥夏ちゃん、また同じこと言ってる。……そうなんだけど、私は遥夏ちゃんからの手紙が欲しいんだよねえ。手紙にしか書けないこと、あるでしょ?」
「そうかなあ?」
「そうだよ、手紙って、形に残るでしょ。形に残るものがあってもいいじゃない?」
「メッセも残るじゃん。スクショ取れるし。」
「遥夏ちゃん、書かない言い訳みたいになってるけど。」
「……そんなつもりはございません。」
背中が極限まで丸くなったわたしに、翠の笑い声が響いた。また、「もう」と言っているけど、さっきより楽しそうだ。
「じゃあ、手紙書いてね。待ってる。」
翠の念を押すような声に、生返事をした。そのあと、また他愛のない話を少しして、電話を切った。電話を切った後に画面を見ると、通話時間は1時間26分と表示されていた。話し過ぎだ。でも、前はきっと、ほぼ毎日このくらい話していたような気もする。
今日は、なにも予定がない日曜日だった。お昼前に目が覚めて、寝ぼけたままリビングに降りた。母は出かけているようで、リビングは静かだった。冷蔵庫から麦茶を取り出して、コップに注いで飲んだ。ふう、と一息ついてから、リビングのテーブルに座った。
テーブルには、プロジェクターのリモコンと、チラシが重ねて置いてあった。なんとなく1枚持ってみると、チラシの間に、市役所からの手紙が挟まっていた。手紙、と認識すると、昨日の翠との電話を思い出した。翠がずっと、手紙にこだわっているのはなんでだろう。市役所の手紙を見ていても、答えは出ないのはわかっているんだけど。
「……書くかあ、手紙。」
目を閉じて少し考えた。手紙を書くには便箋と封筒が必要だ。多分わたしの部屋にはない。家じゅうを探したら一つくらいは見つかりそうだけど、翠が送ってくれたみたいな、ちゃんとした便箋と封筒はあるんだろうか。真っ暗な視界に、ぼんやりと茶封筒が浮かんできて、これ以上想像はするのをやめた。
目を閉じたままため息をついて、ようやく目を開けた。ジャージのポケットに入れていた携帯電話を取り出して、通販アプリを開く。『レターセット』と検索をして、検索結果をスクロールする。白地に緑色の縁取り装飾が施されている封筒が目に留まった。「翠だから、緑色にしたよ」と言ったら、苦笑いされそうだけど、気に入ったので購入ボタンをタップした。
配送予定日が明日になっているのを確認して、検索アプリを開いた。
『手紙 出し方』と入力して、一番上に表示されたサイトをぱらぱらと見る。手紙は郵便物と呼ばれるらしい。定形外郵便なんてものがあることも知らなかった。そこまで読んで、求めている情報ではないことに気付く。
サイトを閉じて、『手紙の書き方のマナー』と見出しがついたサイトを開く。
「……んん?」
お手本と説明書きのある画像を、食い入るように見た。左上に、小さいシールのようなものが貼ってある。
「切手を貼ってください……?」
ふと、ポストから取り出した、翠の手紙を思い出した。白い封筒には、わたしの名前しか入っていなかった。切手なんてものは貼っていなかったし、どこにも翠の名前は書いてなかった。
がたん、と大きな音を立てて椅子から立ち上がって、階段を駆け上がった。勢いよくわたしの部屋のドアを開けて、机に直行する。久しく触っていなかった日記帳を持ち上げると、封筒が見える。
「……ないじゃん、切手。」
白地に深い茶色の文字で、『稲村遥夏 様』とだけ書いてある、封筒が顔をのぞかせた。