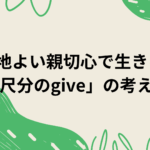この古谷という男は、ものすごく簡単に言えばモテるやつだ。
運動神経が良くて、頭も悪くない、古谷のことを「かっこいい」と言う女子がいたという噂も聞いた。でも、古谷が誰かと付き合う、みたいなことはなかった。
古谷はずっと、翠のことが好きだったらしい。わたしが初めて古谷から恋愛相談を受けたのは中学2年生だったから、そこからずっと片思いしていたのだろう。うじうじしてないで告白すればよかったのに、古谷は、そういうところが惜しいやつだ。
「え、告白できなかったってなに?切ないやつ?それともびびっちゃった感じ?」
部長はここぞ、と言わんばかりに古谷を質問責めしていた。古谷の自転車の前輪が斜めに逸れていくのが、古谷の心境を表現しているようだった。
ひと呼吸入れてから、古谷が口を開いた。
「高塚が引っ越す前に、見たんだよ、俺。」
「……見たって、なにを?」
部長が不思議そうな顔で問いかけた。
「高塚、男と歩いてたんだよ。」
「……え、それだけ?」
「ちょっと、遥夏。ひどいよ、その言い方」
部長はそう言いながらわたしを小突いてきた。自転車の前輪がぐにゃりと曲がった。慌てて自転車のハンドルを切り直すわたしを二人とも気にしていないようだった。部長が古谷の方を不思議そうな顔をして見つめていた。
古谷は部長の視線に耐えられなかったのか、ゆっくりと口を開いた。
「なんか、今まで見たことないくらい、楽しそうな顔しててさ、多分、彼氏なんだろうなあって思って。そんなん見たら、勝ち目ないだろ。」
「彼氏?って聞いちゃえばよかったのに。」
「聞けたら、お前に今、話してねえよ。」
「確かに〜」
部長が明るくうなづいていた。
古谷は黙って自転車を押していた。わたしは、ふーんとだけ言って自転車を押した。
翠に彼氏、いたっけなあ……
もしいたとしたら、わたしにも教えてくれてないのか、それは寂しいな。まあ、それをこの背中がどことなく小さくなった古谷に言っても、意味がないのはわかりきっているけど。
「じゃ、私はここで。ばいばーい。古谷くん、ドンマイ。」
部長はいつもの交差点で別れを告げて、横断歩道を軽やかに歩いていった。わざわざドンマイとかいうあたり、部長はやっぱり大概だと思うんだけど。
「ばいばーい」
部長に向かって声をかけた。古谷は何も言わずに自転車を押していた。部長の背中が見えなくなったあたりで、古谷が口を開いた。
「高塚って、彼氏いたの?」
「……さあ。わたしは、いるって聞いたことないけど。」
「……まじかよ。」
古谷はわかりやすくがっくりとした。
「いない、とは言ってないけど。」
「稲村に言ってないってことは、多分いないだろ。」
わたしもそうであって欲しい、と心のどこかで思っていた。
全部話して欲しいなんて約束はしていないけど、翠とわたしの間に、変な隠し事はないと思っていた。誰にも話せなかったことだって、翠にだけは話すことができた。翠にとって、わたしがそういう存在でいたいと、ずっと思っていた。
そのくらい、わたしにとって翠は大事な存在だ。
「……翠に会いたくなってきたなあ。」
朝にメッセージのやり取りをできて喜んでいたのに、それだけでは寂しいと思ってしまった。
わたしは、翠のいない日常に、簡単に馴染めないようだ。