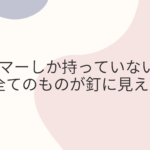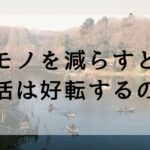鉄板はいくらきれいにしても、また次のお好み焼きを焼き始めると、焦げ付いてくる。
追加注文したお好み焼きも食べ終わり、制限時間が迫ってきたが、誰も話が尽きる様子はなかった。真凛の「デザートを食べたい」という声に全員が反応し、バニラアイスが届くのを待っていた。
もう鉄板の出番がないことはわかっているし、きれいに鉄板をきれいにするのは、店員さんに任せればいいだろう。なのに、わたしの手はへらを手放さなかった。今すぐ逃げ出したいわけではないけど、ちょっとした逃げ場のある安心感が欲しかった。
「おまたせしました。バニラアイスです。」
店員さんの声が聞こえて、みんなの会話が少し止まる。テーブルに置かれたバニラアイスは、ガラスの器まで凍っていた。へらからスプーンに持ち替えて、アイスを食べ始める。
「いや~もう打ち上げも終わりかあ。」
バニラアイスを食べながら、部長が言った。菜々と真凛はうなずきながら、わたしは黙って、バニラアイスを食べていた。
「このあとどうする?どっか行く?」
部長が楽しそうに話し続けた。真凛が少しバツの悪そうな顔をしながら、口を開いた。
「あ~ごめん、あたしこの後、塾ある。」
「まじかあ。真凛、忙しいねえ」
ごめんごめん、と言いながら真凛はアイスを食べた。いいよいいよ、と言いながら部長もアイスを食べていた。
「なんか、こういうの増えるよね、きっと。みんな、ばらばらになっちゃう……寂しっ」
「ええ~、そういうこと言わないでよ、まじで寂しいじゃん」
部長はそう言いながら、スプーンを真凛に向けた。お行儀が悪い、と言いそうになったが、『そういうことじゃない』と言われそうで、言うのはやめた。
「すみません、お時間過ぎているので、お会計をお願いいたします。」
店員さんの声に、みんながゆっくりと、帰り支度を始めた。
打ち上げ会場からの帰り道、さっそくみんなが、ばらばらになった。部長の声掛けでカラオケに行くみんなは、楽しそうに駅の反対側へ消えた。わたしは自転車を出して、このまま家へ帰ろうとした。
「遥夏、途中まで一緒に帰ろう。」
「……うん、帰ろ。」
菜々から声をかけられた。自転車にまたがるのをやめて、わたしは自転車を押し始めた。菜々は、学校の最寄り駅までバスで通っている。当然、今日もバスで学校に来ていた。
「さっき、優子が色々言ってたでしょ。……遥夏、気にしてないかなあって思って。」
菜々が、少し眉尻を下げながら聞いてきた。こういう優しさがあるのが、菜々のいいところだよなあ、と思いながら菜々を見つめた。そして、部長に何を言われたのかを、必死に思い出した。
「……ああ、受験とか塾とかの話? ……気にしてるけど、部長に対しては、別に、なんもないよ」
「なにそれ、どういうこと?」
「受験のことは、ちゃんと考えないとなあって思ったけど、部長がああいう感じなのは、ずっとそうだから気にしてないって感じ。」
菜々の一回目の「なにそれ」は、心配していそうだったのに、二回目の「なにそれ」は、笑いながら言っていた。
「それなら良かった。なんか、最後の最後に仲悪くなるのは、いやだなあと思って。」
菜々は安心したように笑っていた。菜々の優しさを、部長とわたしに分けてほしい。
「仲悪くなるとか、あんま気にしてなかった。……ありがと。」
「なんかね、お姉ちゃんが言ってたんだけど、受験きっかけで友達とギクシャクしたって言ってて。部活のみんなで、そうなるのはちょっと寂しいなあって思って。」
「……え、受験って、そんなことあるの。」
「なんかそうらしいよ、お姉ちゃん、進学校だったから、余計にそうだったのかもしれないけど。」
「ふうん、進学校って大変なんだ。ってか、菜々ってお姉ちゃんいたんだ。」
わたしがそう言うと、菜々は優しそうに笑った。夕焼けでオレンジ色っぽくなった、バス停の看板が見えてきた。
「そうそう、お姉ちゃんいるから、受験の時、大変そうなの見てたの。お母さんも、部活終わったら塾入ったら?って勧めてくれて。……遥夏って、きょうだいはいるんだっけ?」
「いや、いない。……いいなあ、お姉ちゃんいるの。」
「いい時と、悪い時あるよ、お姉ちゃん頭いいから、比較されるとしんどいし。まあ、色々先のこと知れるのはいいんだけどね。」
そういう菜々は、ちょっと困ったように笑っていた。お姉ちゃんとか、お兄ちゃんへの憧れはあるけど、どうやら、良いことだけではないみたいだ。
「受験したことある人の話聞くと、けっこうリアルになるよ。遥夏も、だれかの話聞いてみれば?」
菜々は、年下に話しかけるみたいな優しい声で言った。あれ、妹か弟もいるのかなって聞きたくなった。
「……そっかあ、そうかもなあ。」
「あ、バス来てる。遥夏、こっちまでありがと。気を付けてね。また学校で話そう。」
「うん、……菜々も気を付けてね」
わたしはその場で足を止めて、菜々は扉の開いたバスへ向かった。菜々が機会に腕時計を当てると、『ピッ』と甲高い電子音が聞こえた。菜々の乗車を待っていたかのように、扉が閉まった。
ゆっくりと動き出すバスを見ながら、身近に受験した人を思い浮かべた。
切れ長の穏やかそうな目をしたお兄さんが、頭にふっと思い浮かんだけど、同時に胸がぐっと苦しくなった。