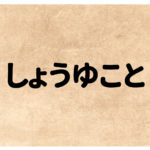菜々と別れて、自転車をこぎ始めた。
予備校とか、進学塾とか、今まで派手な色だな、としか思っていなかった看板が、こんなに自分の身近なものだとは。文字としてだけ認識していたそれが、情報になってわたしを襲ってくる。駅前は情報量が多い。ため息が出そうだった。
派手な看板から目をそらして、自転車をこぎ続けた。
高校受験をしたときは、どうしてたっけ。受験勉強をろくにしていなかったわたしを見かねて、母が、翠のお母さんに相談したとか言っていた気がする。それで、翠の通ってた塾に入れさせられたんだった。そこまで思い出して、信号が赤になって自転車を止めた。
ああ、翠はどうしているんだろうか。今、無性に話がしたい。
「おかえり、……遥夏、お好み焼き食べたの?」
「うん、なんでわかったの」
「そりゃあ、そんな香ばしい匂いしてたらそう思うわよ。そのまま部屋行かないでね、遥夏の部屋、お好み焼きくさくなる。」
そう言いながら母は、わたしに消臭スプレーを渡してきた。わたしはカバンをおろして、ジャージの上着を脱いだ。
床に置いたそれらに、消臭スプレーをばしゃばしゃと振りかけた。今度は消臭スプレーの人工的な甘い匂いが、鼻を襲ってくる。カバンと上着を掴んで、自分の部屋に向かった。
「あ。お風呂湧いてるから、先入ってもいいのよ。」
「はーい」
母の言葉に生返事して、部屋に入った。
携帯電話を開いて、翠に電話を掛けた。コール音を聞きながら、髪の毛がお好み焼きくさいことに気付いた。
匂いと一緒にもやもやが増す。翠、電話出てくれないかな。
「もしもし?遥夏ちゃん?」
「翠!元気!?」
久々に聞いた翠の声に、つい声が弾んだ。翠の笑い声が聞こえてきた。
「元気だよ。遥夏ちゃんも、元気そうだね。」
「いや、いま翠の声聞いたら、元気出た。ありがとう」
「そうなの、遥夏ちゃん、相変わらずだなあ」
そう言いながら、翠は笑っているようだった。
わたしは少し恥ずかしくなって、つられるように笑った。頭を掻くと、またお好み焼きの匂いがする。
「遥夏ちゃんの声聞くの、久々だなあ。どうしたの?」
「いや、なんか、……部活のみんなと色々話しててさ、そしたら、翠と話したくなって。」
「そうなんだ、どんな話してたの?」
少し笑ったまま、でも少し優しい翠の声が聞こえてきた。
「今日、部室の片付け行ってきて。そのあと、みんなで打ち上げしてたんだけど、部長から学校の夏期講習行く?って聞かれてさ。真凛も菜々も、受験勉強するから塾行くとか言ってて。
なんか、あんまりピンと来てなくて。……それで、帰りに菜々に、大学受験したことある人に話聞いてみたら、って言われたんだけど、そんな人周りにいないしさ。みんなどんどん先行っちゃってさ。色々考えてたら、翠のこと思い出して。中三のとき、塾一緒に通ってたなあって。それで、電話した」
翠は、時々「うん」と相槌をしながら、聞いていた。少し沈黙があって、翠の声が聞こえてきた。
「もう、部活引退したんだ。」
「うん、県大会負けて終わった。」
「そうだったんだ。……お疲れさま。……バスケ部のみんなも、受験するの?」
「そうみたい、わたしも一応大学行こうかなあって感じだけどさ、塾とかなんも知らないし」
携帯電話から、翠のう~んと、うなっているような声が聞こえてきた。一気にごちゃごちゃ話過ぎたのかもしれない。
「あ、ごめん翠。ごちゃごちゃ話しちゃった。」
「全然。色々話してくれてありがとう。なんか、懐かしくなっちゃって。遥夏ちゃんから、よくバスケ部の話聞いてたから。」
「そっか、そうだった。」
翠がいたころは、下校時間が一緒になった時に、よく話してたっけ。ずいぶん昔のような気がして、切なくなった。
「遥夏ちゃんには、遥夏ちゃんのペースがあるから、そんな焦らなくてもいいんじゃないかな?高校受験の時だって、遥夏ちゃん、『やばいやばい』って言ってたけど、結局合格したじゃん。だから、大丈夫だよ」
翠はけろっとした声でそう言った。
「……なんか、わたし、そんなやばいって言ってたっけ」
「うん、言ってたよ。夏休みの後半から塾通って、塾のテスト受けてから、ずっと『やばい』って言ってた」
「うわ、なんか思い出してきた。恥ずかしい、やめてよ翠」
「あはは、ごめんごめん。」
そう言ってお互い笑っていた。中三の頃のいろんな思い出が、一気に蘇ってきて、じんわりと汗をかいてきた。
「遥夏ちゃん、やばいとか言いながら、ちゃんとできる子だもん。大丈夫だよ。」
ねっ、と念押しするような声が聞こえてきて、思わず笑ってしまった。
翠は本当にわたしを甘やかす天才だと思う。
もやもやが、気づいたらすっかり軽くなっていた。