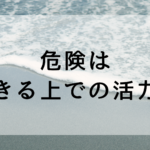先生の声に促された大群に混ざって、三年生の教室がある階まで階段を上った。
階段を上って、少し乱れた呼吸を整えてから、教室のドアを開けた。
無駄にきょろきょろしてしまうのは、きっと少し不安な気持ちもあるのだろう。教室全体から感じる、どことなく探り探りな様子を見て、不安に思っているのは、自分だけではないのかと、仲間を見つけたような気持ちになった。
「なんかさ、三年生、って感じするよね。」
部長はそう言いながら、自分の出席番号に合わせて席についた。
わたしもそれに合わせて、部長の一つ前の席についた。
「……そうなの?どの辺が?」
「……まあ、なんとなく?」
あっけらかんと答える部長に、思わず口をあんぐりさせてしまった。
部長は少し笑いながら話を続けた。
「だってさ、クラスの分け方も変わるし、文系理系で授業ももっと変わるじゃん。」
「……ああ、そっか。」
「それよりさ、春休みの部活終わりに、次の部長誰にする?ってみんなで話した時に、私たちの代、あとちょっとじゃん。ってなんか切なくなったよね。」
しみじみとする部長を見て、わたしは腕時計を見た。
画面が点灯して、今日の日付と時刻が示された。
「最後の大会、六月だもんね。……あとちょっとか~。」
腕時計から目線を上げて部長を見ると、ぶんぶん、と音が出るのではないか、と思うくらいに頷いていた。部長は、頷いた流れのままうつむいていた。
そこからがばっと顔を上げると、部長は感慨深げに口を開いた。
「いや~私はさみしいよ。部活楽しかったし。」
「確かに、あとちょっとだって思うとさみしいね。」
「これからって、そんなことばっかでしょ?『高校生活最後のナントカ』みたいなやつ。」
部長はどこか、遠くを見るようにつぶやいた。
確かに、これから一つ一つにそういう前置きが入るのかと思うと、なんだか切ない気もしてきた。わかっているつもりだけど、『高校生活最後』という言葉に、どことなく胸が締め付けられるような感覚があるのは、まだ受け入れたくない気持ちがあるからなんだろうか。
ぼんやりそんなことを考えていると、風が吹いた。
窓を見ると、風で揺れているカーテンの先に、桜の木が見えた。
三年生の教室は、校庭の桜の木の近くらしい。
「うっわ、桜めっちゃ見えるじゃん。」
楽しそうな声を出す部長に対して、わたしは桜の木に目線を向けたまま頷いた。
「……こういうのにも、『高校生活最後』って、つくのかなあ」
風に揺られる桜の木から、こぼれた花びらを目で追いながらつぶやいた。