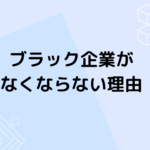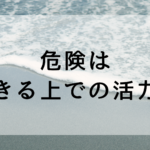午後の授業はいつだって眠たかった。
声のボリュームがでかすぎておかしいと有名な数学の先生の授業ですら、わたしは気づいたら頭がだんだん机に近づいていた。そんな様子のわたしを見た親友はいつも笑っていた。
「今日は豪快だった」
「今日は寝てるかわからないくらいの角度だった」
とか言って、すっかりわたしの評論家になっていた。高校生も残り1年くらいに差し掛かってきていたとき、わたしは最後の1年も変わらず親友と過ごせると思っていた。
「遥夏ちゃん、元気でね。」
そういった親友の顔は、いつものような愛しい笑顔だったけど、夕焼けのおかげかどこか切なく見えた。ちょっと先の未来でさえ、わたしの予想とは大きくことなっていくのだ。そう思ったのは、親友がわたしの斜め後ろの席からいなくなってから気づいた。
「翠ちゃん、引っ越しちゃったんだね。」
母はいつものようにプロジェクターの電源を入れながらわたしに話しかけてきた。
「……うん。」
適当に返事をするわたしを気にせず母は話続けた。
「最近翠ちゃんのお母さんに会ったときに、ちょっと話したんだけどね、実は〜みたいな感じで言われたのよ。幼稚園からずっと一緒だったし、いなくなっちゃうと寂しいわねえ」
「…うん」
あまりにも適当に相づちをうつわたしを見兼ねたのか、母は黙ってプロジェクターに目をやっていた。天気予報と会社で話のネタにするニュースくらい、プロジェクターなんて使わなくてもいいのに。
何度言っても母はスマホと時計は画面が小さくていやだ、テレビもないし、これでいいのよと言ってくる。わたしもいつかこんな大っきい画面じゃないと文字が読めなくなるのか、と思うとぞっとする。視力ってどうやったら維持できるんだろうか。そんなどうでもいいことを考えながらリビングを出た。
「あら、もう朝ごはんいいの?」
「……いってきま~す」
母の問いかけは無視して、スマホと時計の充電を確認した。学校からの通知にため息が出た。なにが今日の時間割だ、配信されようが、学校で同じこと言ってくるのに。
もう、学校の通知うざくない?なんてくだらないことで笑い合える親友もいないのか、と思うとまたため息が出そうだ。学校についてから、友達に挨拶をしたくらいのタイミングで、腕時計が震えた。
表示を見たら、それは翠からのメッセージだった。
『転校してまで追いかけてくる笑』
そんなメッセージと共に送られてきたのは、わたしが今朝ため息が出そうになった時間割が書かれた画面のスクショだった。
『未練やば笑笑』
ふざけたように返事を送ったけど、わざわざわたしに連絡をしてくれたことがなんだか嬉しかった。
翠が引っ越してから、今までより連絡頻度が減った。いつまでもこっちの学校はこうだああだと連絡するのも、なんだか気を遣ってできないでいた。
『遥夏ちゃん、この時間割、午後絶対寝るでしょ笑 怒られないようにがんばってね笑』
翠はどうやら、わたしの評論家であることは変わらないらしい。
『ありがと、いい報告できるようにがんばるわ~笑』
眠っているクマのキャラクターをスタンプを添えてメッセージを返信した。翠からは大爆笑しているウサギが送られてきた。
毎日顔を合わせることはないけど、こうやって簡単に連絡が取れると思っただけでも、だいぶ気持ちが変わった。わたしの生きている時代にこういうツールがあって良かったと思いながら、スマホをブレザーのポケットにしまった。