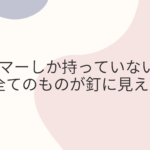古谷と三上は、わたしに聞かせているのか、自分たちで盛り上がっているのか、わからないくらいの雰囲気で、思い出話を始めた。古谷が部活を辞めたいと思っていた時に、三上は部活を辞める、とは思わなかったが、同じように先輩が好きじゃなかったらしい。
というか、同級生の大半は、先輩とそりが合わずに、辞めるか続けるか、みたいな話を頻繫にしていたとか。
ほとんどは、文句を言いながらも続けていく中で、本気で辞めようとしたのが古谷だった。古谷の本気に、周りがどうしよう、と様子を伺っている時に、三上だけが説得しに行ったらしい。
「なんで、古谷の説得したの?」
ふと、頭に浮かんだ疑問を、三上に向けた。三上は、少し古谷に視線を移してから、わたしの方を向いて話続けた。
「古谷が、俺らの学年で一番うまかったから。俺が勝つ前に、古谷に部活辞められたら、勝てないだろ。」
三上の負けず嫌いが、また顔を出していた。古谷は「なんだそれ」と言って顔を背けていた。古谷の様子を見て、三上は楽しそうに笑いながら、言葉を続けた。
「まあ、今は俺の方がうまいかな~。」
「……レギュラー取るのは、俺のが早かったけどな。」
古谷も負けじと、三上に食いついた。
古谷もどこか、負けず嫌いなところがあるらしい。三上が小さく「おお」と楽しそうに声を出して、ベンチから立ち上がった。
「まあ、あの時、……辞めなくてよかったかもな。」
古谷はどちらに言うわけでもなく、ぼそっとつぶやいてコートへ戻った。
三上はその様子を見て、にやりと笑った。そのまま古谷の後を追うようにコートへ戻っていった。
「古谷、素直じゃないな~。俺とバスケやれて楽しいです!って言えよ。」
「うるせえ。勝手な妄想すんなよ。」
古谷はそう言いながら、三上にボールを乱暴にパスした。
コートに戻った二人は、お互いなんだかんだ言い合いながら、練習をし始めた。最初はゆるい空気が流れていたが、次第に二人とも、真剣な表情で練習をしていた。ベンチに一人取り残されて、わたしは二人の様子をぼんやりと眺めていた。
「……わたしは、なんで部活やってるんだろうなあ。」
ボールが地面を跳ねる音にかき消されそうなくらい、小さい声で呟いた。
わたしもバスケは好きだし、負けたくない、という気持ちもある。けど、なにかが二人と違う。その違いが、わたしにはわからなかった。
わかったところで、どうするのかも、どうしたいのかも、何もかもわかっていないけど。わたしは立ち上がって、ベンチの横に置かれたボールを持った。
そのままドリブルを始めて、ゴールに向かってシュートをした。ボールはぼんやりと放物線を描いて、ゴールに弾かれて地面に落下した。
ああ、こういう時って、やっぱり外すんだ。
ただゴールを見つめて、立ち尽くすわたしのところに、ボールが転がってきた。ボールを拾って、一つ深呼吸をしてから、もう一度シュートをした。さっきと同じような放物線を描いて、ボールはきれいにゴールに収まった。
ほんの少しの満足感と同時に、すこしだけ、わたしがわかったような気がした。バスケで得られるこの満足感が、何事にも代えがたいくらい、わたしは好きなのかもしれない。3人で練習を始めて、気づいたら3時間は経っていた。
「今日はもう終わりにするか。腹減ったし。」
三上の一言で、練習会は終了した。3人で片づけをして、帰る準備をした。
「せっかくだから、なんか食ってから解散しようぜ。」
三上の提案に、古谷は「おう」と短く返事をした。
「……稲村は?」
古谷に声をかけられて、一瞬悩んだが「行く」と返事をした。
すっかり忘れていたが、家に帰る時間は、遅い方がいいことを思い出した。母も、母の友人もおしゃべりだ。3時間であちらが解散になるかは、微妙なところだった。3人で公園を出て、駅ビルまで向かって歩いた。
「稲村、今日どうだった?」
古谷が突然質問をしてきた。
「どうって……まあ、楽しかったよ。」
「それなら良かった。」
わたしがそう答えると、古谷は頷いた。
「……わたし、多分周りが誰でも、バスケできるんだよ。バスケやってるのは楽しいから。」
わたしがひとり言のように話し始めたのを、二人は黙って聞いていた。
「ちょっとでも上手になりたいし、上手になった、ってわかった時ももっと楽しい。それを、わたしは長く続けたい。……だから、部活もずっと続けてるんだろうなあって。」
古谷が、また口を開いた。
「おう。部活、がんばれよ。」
「なんで急に上から目線なの。」
「そんな事ねえよ。」
「素直じゃないねえ、古谷は。」
古谷が怒ったような表情をするのを見て、三上はまた楽しそうに古谷をいじっていた。
「理由はなんでもいいけどさ、せっかくなら勝ちたいし、面白くやろうぜって俺は思ってるよ。」
三上は少し真剣な表情をして、そう言った。
古谷は、また「おう」と短く返事をした。わたしも頷いた。
理由はわからないけど、今日のことを、忘れちゃいけないような気がした。