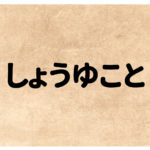ゴールを見つめている後輩の瞳に、光はなかった。どこにも焦点はあっていないし、体が動き出す気配も感じられなかった。この姿は、かつてのわたしだ。わたしのせいで負けた、そう思った時のわたしだ。
なにか言葉をかけなければ、そう思った。後輩に伝える言葉なんて、なにも思いついていない。ただ、このままにしてはいけない。その思いだけが、わたしの足を、後輩へと動かした。
「……あの、さ……」
なんとも歯切れの悪いわたしの声に気付いた後輩が、こちらを向いた。瞳は、近くで見ても、やはり光はなかった。ひとりだけ、真っ暗闇にいるみたいだった。
「……すみません……最後の大会なのに、私のせいで……」
「いや、誰のせいでも、ないでしょ。」
わたしは、後輩の言葉にかぶせるように言い放った。
どこかで、これ以上、後輩に自分を責めるような言葉を、言ってほしくなかったのかもしれない。驚く後輩の顔を見ながら、言葉がまたぽつりぽつりと出てきた。
「わたしのせいで、なんて言わないでほしい。誰かのせいにして、試合が、勝ったことになるわけじゃないし。それよりも、最後まで点を取りに行った、自分を大事にしてよ。2年生で、レギュラー取って、最後まで試合出れて、わたしやるじゃん、って思っててよ。」
「……はい……」
小さい声で、返事が聞こえてきた。
きっと納得していなんだろう。わたしだって、あの時は何を言われたって、気持ちをなにも消化できていなかった。
「もし、なんかもやもやしてるなら……バスケ、楽しんでほしい。」
「えっ」
「わたしも、中学の最後の大会で、同じようなことあって。最後にわたしがシュート外して、そのまま試合に負けた。ずっと、悔しかったし、もっと練習しないといけない、もうわたしのせいで負けたくない、って思ってた。」
「そうだったんですか……」
「負けたくないって思って、必死こいて練習したって、負けることもあるんだよ。そんなことわかってる、でもバスケが楽しかったから練習してた。何が楽しいって、自分がうまくなるのが楽しかった。『できない』ことが、一つずつ『できる』になるのが楽しかった。」
言葉がどんどん出てくる。わたしにしては、珍しいことかもしれない。
「だから、自分なりの、楽しいバスケを、部活でやってほしい。それが、きっと自分を助けてくれる。」
「……はい。」
後輩は、さっきよりも少し大きくなった声で、返事をしてくれた。
「バスケ、やってくれて、ありがとう。」
いまのわたしにできる、精一杯の笑顔で言った。
後輩は、驚いていたけど、少しだけ笑ってくれた。瞳に、光が戻ってきたみたいだった。
遠くにいた部長から、「おーい」と呼ばれたので、二人で並んで歩いた。後輩が、どう思ったのか、わたしにはわからない。なんであんなに言葉がすらすら出てきたのかも、自分でもわからない。一つだけわかるとしたら、後輩と同じ瞳をしていた、あの時のわたしに、かけてあげたかった言葉だということだ。
「ねえ、これからどうする?」
会場から出て、帰宅途中の電車に揺られながら、部長が、話しかけてきた。
「え、……家帰って、ご飯食べて、あとは寝る。」
「ちょっとお、そういうことじゃないんだけど。」
部長は、わざとらしく怒っていた。
「2年生の中から、誰を部長にするか決めるでしょ、うちらの打ち上げどうするか決めるでしょ、あと部室に置いた荷物も片づけなきゃ。ほら~、やることいっぱいじゃん。」
「……そっか。」
部長は「まったくもう」と言いながら、携帯電話に目線を落とした。なにかをタップしてから、わたしに画面を見せてきた。
「打ち上げ、こことかどうかな。あ、あとね、部長の候補は決まってるから、あとはあっきー先生と話すだけなんだよね。部室の片づけも、部長決まって、後輩ちゃんたちに挨拶したあとでいいかなあって。いや~大会終わっても大変だわ~」
部長は、3つともごちゃまぜで話してきた。
わかるけど、整理が追いつかない。大変とか、なんだかんだ言いながら、部長は元気そうだし、楽しそうだ。
細かいこれからのことは、よくわからなかった。部活を引退したら、高校生活は残り9か月ほどだ。それまでに、わたしは何をするんだろうか。
「部長、これからも、よろしく。」
突然、わたしの口から出た言葉に部長はびっくりしていた。
「え、どうしたの遥夏。」
「部活なくなっても、たまには遊んでよ」
「たまには、というか、クラス一緒じゃん。遊ぶに決まってるじゃん。授業中寝てたら起こすし。」
「それ、わたし遊ばれてるじゃん。」
そういうと部長は「うけるー」と言いながら、手を叩いて笑った。
やっぱり楽しそうだ。
これから、なにをするにしても、まだまだ楽しいことは、あるのかもしれない。