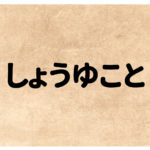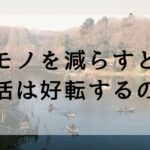前回は、砂糖が17世紀では甘味料だけでなく、薬品や装飾品として扱われたことをお伝えした。また、高級品で知られる物同士をかけ合わせた「砂糖入りの紅茶」が当時のステータスシンボルであることを紹介した。今回も『砂糖の世界史』 (川北 稔)より、甘い砂糖に関するほろ苦い歴史について考えていきたい。
砂糖はどこから来たのか
このような問いをすることなく、意識せずに手にできる社会で生きているが、それを紐解くキーワードとして「プランテーション」がある。
プランテーションとは、ほかの作物をほとんどつくらずにヨーロッパを中心に世界に売れるものだけを栽培する農園のことで、そのように経済や農業の在り方を「モノカルチャー経済」という。17世紀のカリブ海はヨーロッパから来た白人が支配した島にモノカルチャーの農業が展開され、その労働力としてアフリカから来た黒人の奴隷が住むようになった。
プランテーションで栽培されていたのが、砂糖の原料であるさとうきびである。さとうきびを植え付け、刈り入れ、砕いてジュースを絞り出し、煮詰め、精製し、茶色の原糖が完成する。それらをヨーロッパで精製して純白の砂糖を完成させていた。
どの工程も重労働で、できるだけ短時間で運搬を済ます必要から時間を正確に守って働く必要があった。
「時は金なり」というスローガンをかかげて、時間を守らせようとした。そこにある全てのものが、砂糖を作る目的のみに存在した。
奴隷船
プランテーションで働く奴隷たちは、アフリカから大西洋を超えて、ジャマイカやバルバドスに運ばれたようだ。
その航海自体が悲惨なもので、可能な限り奴隷を積み、飲み水も十分に用意がなかった。そのため、航海の途中で脱水症状を起こしたり、伝染病にかかったり、海に飛び込んで自殺するケースが後を絶たなかったといわれている。
カリブ海についた奴隷は、競り市にかけられ、プランテーションの持ち主へ売られていった。アフリカにはない病気や、気候条件、生活環境のため、現地慣れする期間で数十パーセントが亡くなっていった。
16世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパ人(なかでもポルトガル人・イギリス人・フランス人がこの商業に熱心になった)が運んだ黒人奴隷は最低でも1000万人以上と推定されいてる。奴隷貿易は、失敗することもあったが、成功すると元手の二倍になるほどの儲けが得られたといわれている。砂糖商人の多くはイギリスに住み、上流階級・ジェントルマン階級の人間として暮らすようになった。彼らは仲間の国会議員を40人以上抱えており、イギリスの政治を思うように動かせていた。
アフリカの国々
働き盛りの人々を多数連れ去られたため、残された家族や奴隷にされた人の悲しみが溢れる状態では、アフリカ社会は発展しにくいものでした。アフリカが現在に至るまで「開発途上」の状態にある歴史的理由の一つが、ここにあるのである。
大量の、安い、強制的に働かされる黒人奴隷の汗と血と涙で、生産されたのが砂糖である。
「SAVE AFRICA」などのスローガンで医療、衛生、農業など住民の生活向上などを目的とする活動がある。支援団体などに当時奴隷貿易に熱心だったヨーロッパ人があったときには、過去に種を撒いたものに対して世紀を超えた刈り取りが行われていることを意識したい。